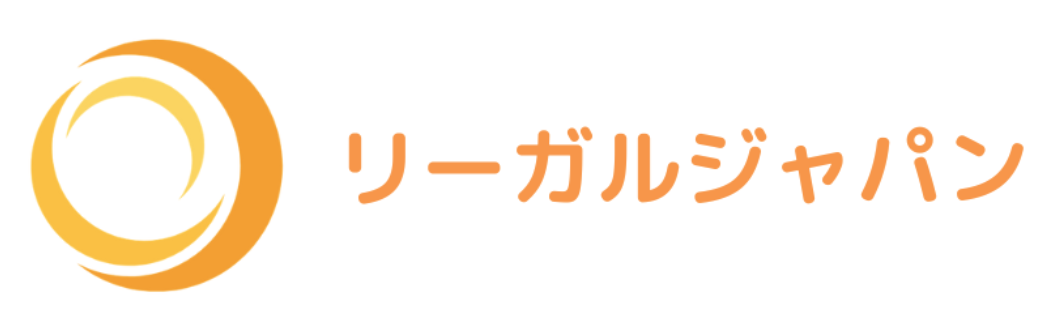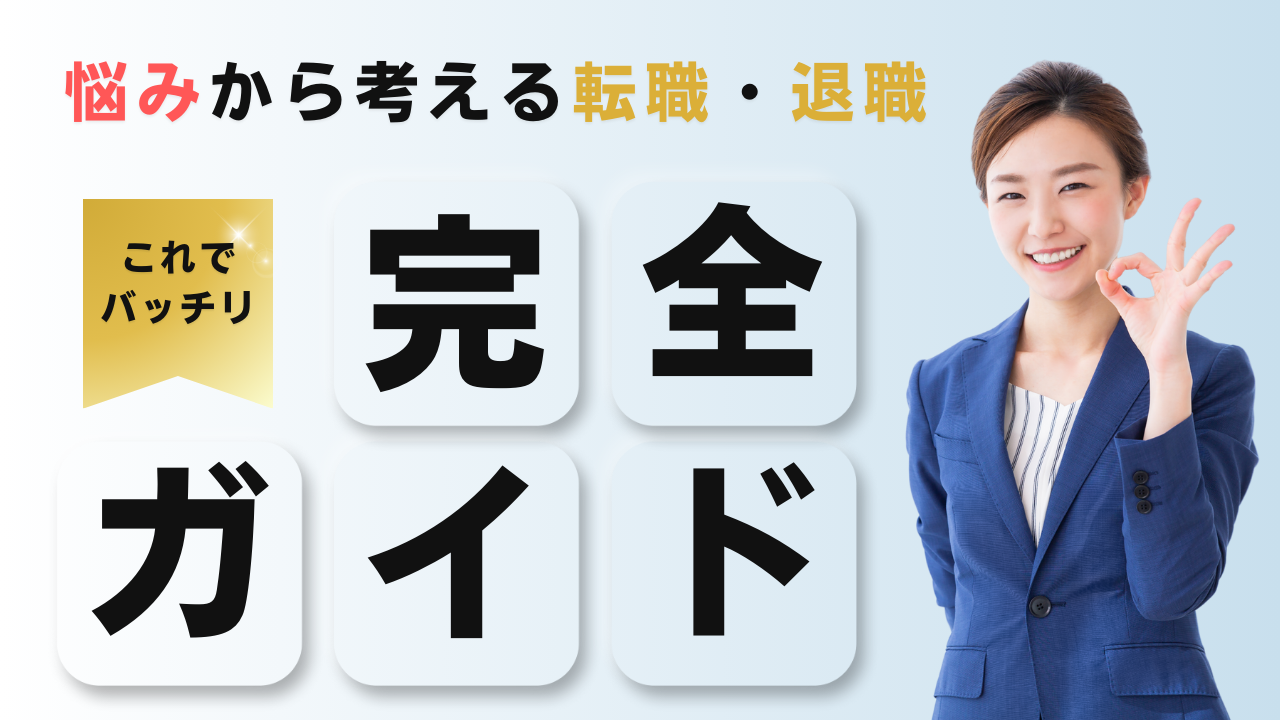仕事で覚えることが多すぎる原因は、情報過多や効率的な学習方法が分からないなどがあります。対処法としては情報の分類や整理、学習方法を変更したりツールの導入が効率的です。また、健康管理も大切で、ストレスをかけないようにしたり、働く環境を整えたりすることも必要です。

仕事で覚えることが多すぎる原因はなんだろう?
日々増え続ける仕事の量、記憶しなければならないデータや情報。
頭に入らない…と感じたことはありませんか?
この記事では、覚えるべきことが多すぎると感じる原因と、その解決策について詳しく解説します。
- 仕事量の多さ
- 自身の記憶力や情報処理能力の問題
- 効率的な知識の管理方法が身についていないため
頭に入らない時の対処法はどうすればいいのでしょうか?
一口に記憶といっても、そのメカニズムは単純なものではありません。
効率的に情報を記憶、利用するためには、どのようなアプローチが必要なのでしょうか。
仕事で頭に入らないと感じるあなたに対する具体的な解決策を提供するべく、本記事を用意しました。
あなたのビジネスライフを劇的に変えるかもしれません。
仕事で覚えることが多すぎる原因
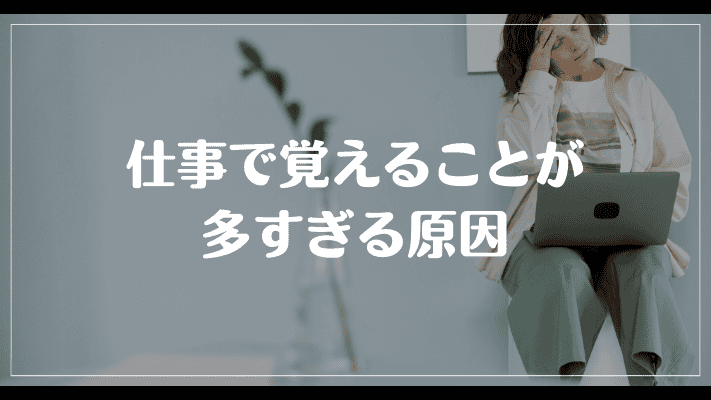
仕事では様々な情報が飛び交い、学ぶべき内容が日々増え続けます。
一体何が問題なのでしょうか。
その原因には様々な要素が存在します。
- 情報過多
- 負荷の高さ
- 効率的な学習方法がわからない
それぞれ具体的に見ていきましょう。
情報過多
新社会人が直面する、覚えることが多すぎて頭に入らない現象。
その一因として、情報過多が挙げられます。
- 一度に得る情報量の多さ
- 情報の更新頻度の高さ
- 必要な情報と不必要な情報の見分けがつかない
一度に得る情報量の多さ
情報過多の一つ目の要素は、一度に得る情報量の多さです。
新人社員に必要な情報は実に多岐にわたります。
- 企業の禁則事項
- 業界知識
- 内部の人間関係
生まれて初めて体験する業界や会社で働くとなると、これまでの教育環境では学んでこなかった専門知識や技術まで、すべてが未知の領域となります。
この膨大な情報を一度に学ぶために頭をフル回転させることになり、それが誰しもが感じる情報過多の状態へと繋がります。
情報の更新頻度の高さ
二つ目の要素は、情報の更新頻度の高さです。

特にIT業界などは日々新たな技術が開発され、常に最新の情報をキャッチアップしなければならない状況が続きます。
これに加えて、企業内でも日々変わる業務内容や突発的に発生する問題など、情報は絶えなく更新され続けます。
新入社員にとっては、まず基本的な情報を覚えている間に次の新たな情報が発生し、振り回されてしまうことも。
必要な情報と不必要な情報の見分けがつかない
そして3つ目は、必要な情報と不必要な情報の見分けがつかないです。
仕事で耳に入ってくる情報は全て新鮮で、どれが重要で何がただの雑音なのか見分けるのも一苦労。
完全に理解しようとするほど、頭はパンク寸前となってしまいます。
このことが新入社員が覚えることが多すぎて頭に入らないと感じる一因となるのです。
負荷が高すぎる
仕事を覚える上でのもう一つの壁となるのは、負荷です。
- 頭のキャパシティをオーバーフローさせる作業量
- 高い精神的ストレス
- 不適切なレストタイム
頭のキャパシティをオーバーフローさせる作業量
仕事で覚えるべき情報量は多く、各人有する記憶力や集中力にも限界があります。
- 会社の業務内容
- 社内ルールやマナー
- 先輩方の名前など
全て覚えなければならず、内容が膨大になります。
頭のキャパシティをオーバーフローさせ、一時的に脳の機能が低下し、物事を学ぶ能力が落ちてしまう原因となるのです。
高い精神的ストレス
高い精神的ストレスも影響します。
- 新しい環境に馴染むこと
- 上司や同僚との人間関係
- 業務遂行でのミスなど
身体的・精神的に疲労が溜まってしまうと、脳にも影響を及ぼし、学習能力を損なう可能性があります。
不適切なレストタイム
不適切なレストタイムも考えられます。
休息時間が不足していると、脳の機能が十分に回復できず、学習効率も落ちる可能性があります。
特に長時間の一気仕事は、脳への負担が大きいだけでなく、その後の休息によっても回復しきらないことがあります。
効率的な学習方法がわからない
最後の要素としては、効率的な学習方法がわからないことです。
- 子供のころの学習方法に固執している
- 適切な学習ツールの選択ができていない
- 学習の習慣がない
子供のころの学習方法に固執
一つ目の、子供のころの学習方法に固執するという点は意外と見落とされがちですが、大人になっても子供のころの学習方法をそのまま持ち越している人は少なくありません。

大人になって学ぶ内容は子供のころとは大きく異なるため、新たな学習方法を身につけることも必要です。
適切な学習ツールの選択ができていない
二つ目の、適切な学習ツールの選択ができていない」といった問題もあります。
近年ではIT技術の進化により、多くの便利な学習ツールが開発されています。
うまく利用することで、情報の取捨選択や整理、ま記憶の定着化に役立ちます。
効率的に情報を覚えるためには重要なツールとなるでしょう。
学習の習慣がない
最後に、学習の習慣がないという問題です。
学校を卒業して社会人になると、新たな知識を学ぶということが自然に少なくなってしまいがちです。
自ら学ぶという習慣がない人は、試行錯誤しながら詰んだ知識を学ぶことに時間がかかり、結果として覚えることが多すぎるという状況を招いてしまいます。

自分に合った学習法を見つけることで、大量の情報に立ち向かい、成長を遂げることが可能です。
仕事で覚えることが多すぎて頭に入らないときの対策法
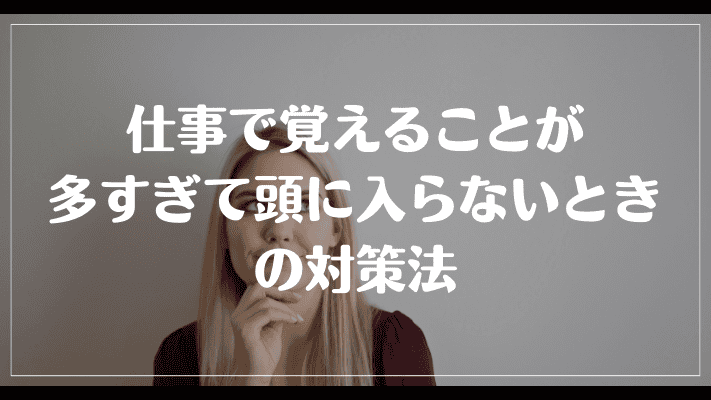
仕事や学習において、思い悩む方は少なくありません。
もしかすると、仕事はどのくらいで覚えられるのか?と自身の学習力に疑問を抱き、仕事が覚えられないということを発達障害の一環と捉えてしまうかもしれません。
必ずしもそうとは限りません。
自身の学習力を最大限に活かすための具体的な対策法を3つの段階に分け、深く掘り下げてみましょう。
情報の分類・整理
まずは、頭の中に入れた情報をうまく分類・整理することから始めます。
情報が大量に入ってきたときには、どれが重要でどれがそうでないかを見分ける能力が求められます。
優先度の見分け方
情報の優先度を見分けるためには、あなたの目標達成にどれだけ貢献するか、という視点が重要です。
具体的な目標を設定し、それに基づいた判断基準をもつことで、情報の優先度を見極めることができます。
今週の報告書作成に必要な情報、1ヶ月後のプレゼンテーションのための情報といったように、情報を目標達成に必要なもの、それ以外で区分けすることができます。
マインドマップで整理
情報整理のためのツールとしてマインドマップがあります。

マインドマップは視覚的に情報を整理し、関連性を明確にするのに非常に有効な手法です。
まずは一つのテーマを中心に据え、そこから連想されるキーワードを枝分かれさせていきます。
その結果、ある情報がどのように繋がっているのか、全体像が見えやすくなります。
一日の学習計画を立てる
一日の学習を計画することも重要です。
学習時間やその内容を明確にすることで、効率的に学習が行えます。
各事項の予測所要時間を記載し、その後でその日の学習の優先順位をつけると良いでしょう。
適切な学習時間の配分ができ、情報のキャパシティオーバーを防ぐことが可能になります。
健康管理
情報の分類・整理だけではなく、健康維持も大切な要素です。
身体的、精神的な健康状態が優れていると、学習効率は格段にアップします。
レストタイムの適切な取り方
人間の脳は長時間集中することが難しいので、適切な休息が必要です。
25分学習した後に5分の休息を取るという、ポモドーロテクニックが有名です。
休息をうまく取り入れることで、脳への負担を軽減し、情報の吸収力を高めることができます。
ストレスマネジメント
ストレスは脳の働きを阻害します。
ストレスを感じていると、落ち着いて情報を整理することが難しくなります。
ストレスを解消するためのリラクゼーション法や、好きな音楽を聴く、散歩をするなどを活用してみましょう。

自分に合ったストレス解消法を見つけ、継続的に行うことで、脳の健康状態を保つことができます。
快適な環境づくり
学習や仕事を行う環境が整っていると、集中力は増します。
物理的な環境だけでなく、気分を明るくするための環境作りも重要です。
- 自分が好きな音楽を流す
- お気に入りの飲み物を用意するなど
小さな工夫から始めてみましょう。
効率的な学習方法を身につける
自身にとって効果的な学習方法を見つけ、それを継続することも重要です。
自分の学習スタイルを理解し、それに合った学習法を探りましょう。
学習方法の更新
学習方法は一つだけでなく、多岐にわたります。
- オンライン講座を利用
- チューターに教わる
- 一緒に学習する友人を見つけるなど
何か新しい学習方法を試すことで新たな視点を得ることができます。
効果的な学習ツールの導入
効果的な学習ツールを使うことも有効です。
- フラッシュカードを作成する
- メモを活用する
- デジタルノートを使用するなど
自分のライフスタイルに合わせてツールを選び、上手に情報の整理や管理を行いましょう。
学習の習慣化
一度学習しただけでは、その情報が長続きしないものもあります。

日々のルーティンに学習を組み込み、継続することが大切です。
一日に多くの時間をかける必要はなく、短時間でも継続的に学習を行うと効果的です。
働く環境を変える
上記を試してもなお、仕事で覚えることが多すぎてついていけない場合は会社の業種や職種が自分に合っていないのかもしれません。
会社の仕組みを変えることは困難であり、大切な人生の時間を無駄にしてしまいます。
勢いで転職すると後悔しやすく、焦らず慎重に転職活動を進めることも大切です。
こちらの記事では、私が転職に失敗した経験をもとに、後悔しない転職(退職)を実現するために重要なことをまとめています。
【悩んでるあなたへ】転職?退職?自分にぴったりのサービスを見つける方法
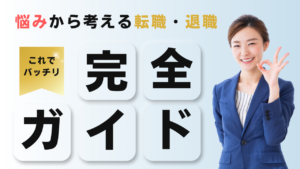
退職代行サービス比較表
| サービス | リーガルジャパン |  男の退職代行 男の退職代行 |  わたしNEXT わたしNEXT | 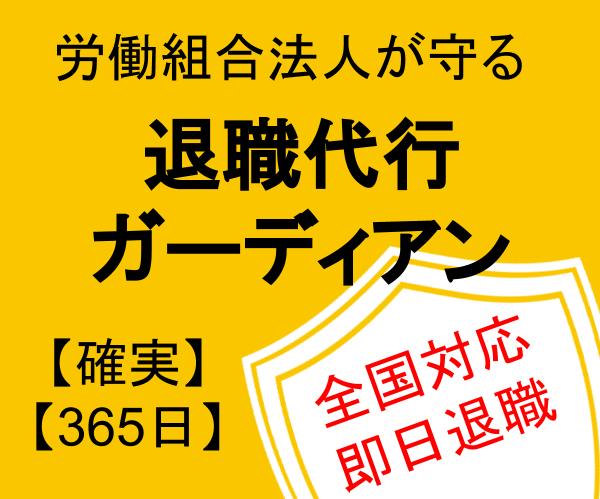 退職代行ガーディアン 退職代行ガーディアン |
| おすすめ ポイント | 安心安全の労働組合運営 | 即日退職できる | 女性専用 | おすすめの退職代行 |
| 特徴 | 職場への連絡不要 LINEで24時間相談 手続きはすべて郵送OK | 「ツラい」「言い出せない」から開放 顧客満足度No.1 | 退職相談は無料 女性専用 わたしらしい自分へ | 労働組合だから安心 追加料金は0円 |
| おすすめ度 | (5 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | (4 / 5.0) |
| 主な対象年代 | 20代〜50代 | すべての男性 パート・アルバイトもOK | すべての女性 パート・アルバイトもOK | 20代〜50代 |
| 対象エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |
| 利用料金 | 25,000円 ・無制限のチャット相談 ・有給消化サポート | 26,800円 (退職相談は無料) パート・アルバイト 19,800円 | 29,800円 (退職相談は無料) パート・アルバイト 19,800円 | 24,800円 (相談は無料) |
| 監修者コメント | 実績と金額で選ぶならコレ | 男性やパート・アルバイトにおすすめ | 女性の不安を解決 | ー |
| 公式サイト | 無料相談はこちら https://lp.legal-japan.net/ | 詳細を見る https://taishoku.to-next.jp/ | 詳細を見る https://taishoku.to-next.jp/w/ | 詳細を見る https://taisyokudaiko.jp/ |
まとめ:仕事で覚えることが多すぎるときは1つ1つ情報整理を
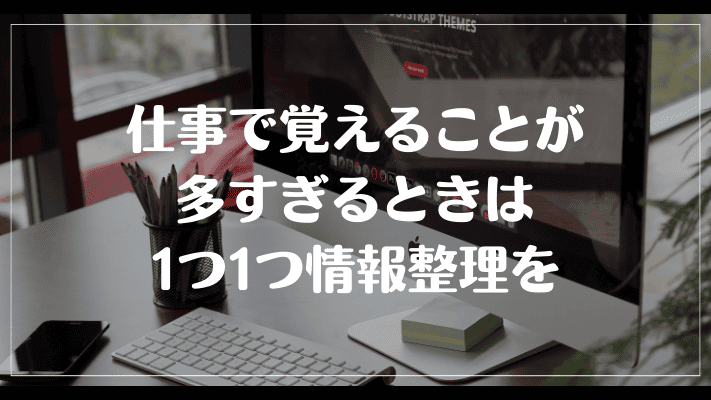
情報の整理や健康管理、効率的な学習方法を利用し、自分自身の知識を上手に管理することで、情報発信時代の中でも自己成長が可能となります。
それぞれの対策法を組み合わせて利用することで、相乗効果も得られるでしょう。
一つずつ試してみて、自分に合った方法を見つけてみてください。
覚えるのが苦手という自己認識を、学習力を活かすスキルを持っているという認識に変えて行くことができるでしょう。
また、転職すべきかどうか悩んでいる人は、焦らず慎重に転職活動を進めることも大切です。
こちらの記事では、私が転職に失敗した経験をもとに、後悔しない転職(退職)を実現するために重要なことをまとめています。
【悩んでるあなたへ】転職?退職?自分にぴったりのサービスを見つける方法
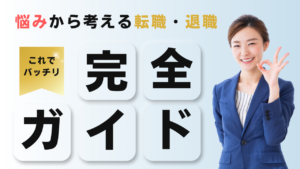
退職代行サービス比較表
| サービス | リーガルジャパン |  男の退職代行 男の退職代行 |  わたしNEXT わたしNEXT | 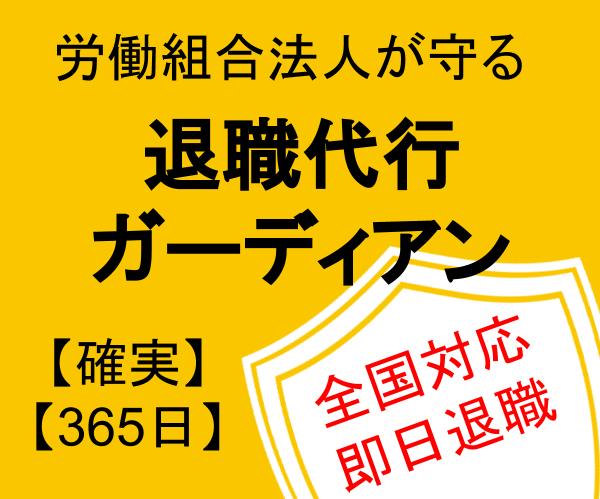 退職代行ガーディアン 退職代行ガーディアン |
| おすすめ ポイント | 安心安全の労働組合運営 | 即日退職できる | 女性専用 | おすすめの退職代行 |
| 特徴 | 職場への連絡不要 LINEで24時間相談 手続きはすべて郵送OK | 「ツラい」「言い出せない」から開放 顧客満足度No.1 | 退職相談は無料 女性専用 わたしらしい自分へ | 労働組合だから安心 追加料金は0円 |
| おすすめ度 | (5 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | (4 / 5.0) |
| 主な対象年代 | 20代〜50代 | すべての男性 パート・アルバイトもOK | すべての女性 パート・アルバイトもOK | 20代〜50代 |
| 対象エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |
| 利用料金 | 25,000円 ・無制限のチャット相談 ・有給消化サポート | 26,800円 (退職相談は無料) パート・アルバイト 19,800円 | 29,800円 (退職相談は無料) パート・アルバイト 19,800円 | 24,800円 (相談は無料) |
| 監修者コメント | 実績と金額で選ぶならコレ | 男性やパート・アルバイトにおすすめ | 女性の不安を解決 | ー |
| 公式サイト | 無料相談はこちら https://lp.legal-japan.net/ | 詳細を見る https://taishoku.to-next.jp/ | 詳細を見る https://taishoku.to-next.jp/w/ | 詳細を見る https://taisyokudaiko.jp/ |